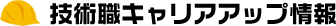労働安全衛⽣法に基づく労働安全衛生診断とは? 受け方を紹介します。
2017/02/06
労働安全衛生診断とは、労働災害を発生させた場合や労働安全衛⽣法78条第1項の規定に基づいて労働局長に安全衛生改善計画の作成を指示された時などに、受けるものです。労働安全・衛生コンサルタントによって行われ、事業者が望めばそのまま労働安全・衛生に関する指導も受けられます。
そこで、今回は労働安全衛生診断や労働安全衛生法についてご紹介しましょう。
この記事を読めば、労働安全衛生診断を依頼した方がよい場合が分かり、労働安全衛生法に関する知識も深まるでしょう。職場の安全管理や衛生管理に関わる仕事に就いている方は、ぜひこの記事を読んでみてください。
1.労働安全衛生の基礎知識
はじめに、労働安全衛生の基礎知識についてご紹介します。どのような法律や規則に基づいているのでしょうか?
1-1.労働安全衛生とは
労働安全衛生とは、従業員が安全で衛生的に仕事ができるように定められている規則や法律の総称です。また、職場で安全に働けるように安全管理や安全教育をする安全管理者、衛生管理をする衛生管理者という職務もあります。職場によっては安全衛生委員会が設けられているところもあるでしょう。
1-2.労働安全衛生法とは
労働安全衛生法とは、労働者の安全と衛生に対する基準を定めた法律です。かつては労働基準法の中に労働安全衛生に関する項目がありましたが、1972年(昭和47年)に独立した法律になりました。この法律に基づいて労働災害の防止に関する措置が定められたり、安全管理者・衛生管理者・産業医の選任が義務付けられたりしています。法律ですから、当然守らなければなりません。違反すると罰則があります。
1-3.労働安全衛生規則とは
労働安全生衛生規則は、労働安全衛生法をより細分化した決まりです。たとえば、労働安全衛生法では産業医を選任しなければならない、と定められています。規則の方では「このような業務を行い、何人以上の従業員が所属している場合は産業医を選任しなければならない」とより細かく定められているのです。労働安全衛生法と規則はセットで運用されます。
1-4.法律の目的や必要性
労働安全衛生法は
- 危険防止基準の設定
- 責任体制の明確化
- 労働災害の防止
- 安全で衛生的な職場づくり
などを目的として定められています。ちなみに労働安全衛生法はすべての職場で適用される法律です。たとえデスクワークが中心のオフィスであっても適用されます。
2.労働安全衛生診断とは
この項では、労働安全衛生診断の内容や実施できる人、実施が推奨される場合をご紹介します。どのような診断なのでしょうか?
2-1.労働安全衛生診断とは
労働安全衛生診断とは、診断を依頼された場所の設備や作業方法・作業手順・作業環境の中に潜んでいる労働災害の原因を見つけだし、改善の指導をすることです。職場の安全管理や衛生管理は前述したように、選任された安全管理者や衛生管理者が行います。しかし、労働災害の芽に気づいていないこともありますし、気づいていてもどのように改善していいか分からないこともあるでしょう。第三者が診断することにより、労働災害を未然に防ぎ職場環境を改善する効果が期待できます。
2-2.労働安全衛生診断が行える人とは
労働安全衛生診断は、労働衛生コンサルタント・労働安全コンサルタントが行います。コンサルタントはそれぞれ国家試験に合格した有資格者で、企業の求めに応じて診断や指導を行っているのです。無資格者が診断を行うことはできません。
2-3.労働安全衛生診断が必要される時とは
労働安全衛生診断は、
- 労働災害が発生した時
- 機械設備や作業環境等の改善を行いたい時
- 新しい設備を入れたり新しい工法を導入したりする時
などに受けることが必要とされます。診断を受けることは義務ではありませんが、労働安全衛生対策をしっかりと行っているという証明にもなるでしょう。
2-4.実施の流れや費用などについて
労働安全衛生診断を受けたい場合は、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの事務所などに依頼します。日本労働安全衛生コンサルタント会も各都道府県に一つずつ支部があり、労働安全衛生診断を請け負っていますので、利用してもよいでしょう。安全診断と衛生診断、どちらか片方だけでも受けることができます。同時に両方の診断を受けることも可能です。コンサルタントには守秘義務がありますから、企業秘密などが外部に漏れる心配はありません。費用は1日診断をしてもらって10万円前後が相場です。診断の後で指導を受ける場合は別途料金が必要になります。
3.労働安全衛生診断に関する資格について
この項では、労働安全衛生診断をすることができる資格についてご紹介します。資格取得を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
3-1.労働安全衛生診断が行える資格とは
労働安全衛生診断が行える資格は、労働安全コンサルタントと労働衛生コンサルタントの2つです。両方の資格を取得することも可能ですがそれぞれ実務経験がないと取得ができませんので、どちらか片方の資格を取得して安全か衛生の診断をしたり指導をする方がほとんどになります。
3-2.労働安全・衛生コンサルタントの受験資格
労働安全と衛生のコンサルタントの資格を取得するには、労働安全や労働衛生に関する実務経験を積んだ方が受験できます。最短で理系の大学を卒業後に3年です。
また、労働安全コンサルタントは技術士・第1種電気主任技術者・1級建築士試験合格者といった資格を持っていても受験資格が得られます。
労働衛生コンサルタントは、医師・歯科医師の資格を持った方は職務経験なしでも受験資格が得られるのです。この他薬剤師や保健師の資格を取得している場合は、一定期間労働衛生に関する実務経験を積めば受験資格を得られます。
3-3.資格を取得するメリット
労働安全・衛生コンサルタントの資格を取得すると、会社に所属しなくても診断が行えます。つまり、独立が可能です。会社に所属し、長い間職場の衛生管理や安全管理を行ってきた方で、定年後も働きたいという場合も資格を取得すれば選択肢が広がります。また、資格を取得しておけば転職にも役立ちますし資格手当がつくこともあるでしょう。
3-4.試験内容・実施日・申し込み方法など
3-4-1.労働安全コンサルタント
労働安全コンサルタントの試験は、産業安全一般・産業安全関係法令・専門科目(機械・電気・化学・土木・建築から一科目選択し安全について記述する)の3科目です。これに合格した方のみ、二次試験として口述試験があります。なお、資格に合格すればどのような職場でも安全診断を行うことは可能です。ですから、得意分野の安全を選択しましょう。
試験は、安全衛生技術者試験協会が年に一度10月上旬に実施します。二次試験は1月中旬です。申し込み方法は必要書類と受験申込書を協会へ郵送するか窓口へ直接提出してください。インターネットからは申し込みできません。詳しい応募方法は協会のサイトで確認しましょう。
3-4-2.労働衛生コンサルタント
労働衛生コンサルタントも、安全コンサルタント同様に一次試験・二次試験を行います。一次試験は3科目あり、労働衛生一般・労働衛生関係法令の2科目に加えて、健康管理・労働衛生工学のうちどちらかを選択し記述するものです。どちらを選択しても合格後に行える業務に差はありません。二次試験が口述試験なのも同様です。試験日は安全コンサルタントと同日になります。こちらも詳しいことは安全衛生技術者試験協会のサイトで確認しましょう。申し込み方法も同じです。
3-5.費用や試験会場など
それぞれのコンサルタントの受験料は、同額の24,700円です。一次試験も二次試験も実施される都市が限られていますので、地方在住の方は泊まりがけで受験を行う必要があります。ですから、計画は早めに立てましょう。
3-6.難易度と合格率
労働安全・労働衛生のコンサルタントの難易度はどちらも難関となっています。独学で勉強される方も多い資格ですが、一度は受験対策講座などを受けることがおすすめです。合格率はどちらも25%程度で、100人以上が受験し合格する方は最終的に25名ほどとなります。1度不合格になったからとあきらめずに何度も挑戦しましょう。
3-7.おすすめの勉強方法
労働安全・労働衛生のコンサルタントの勉強法は
- 受験対策講習会に参加する
- 通信教材を利用する
- 独学で勉強する
の3つです。独学で勉強する場合はとても大変ですから、ある程度独学で勉強した後で講習会に参加してもよいでしょう。なお、コンサルタントの参考書はあまり一般書店では販売されていません。日本労働安全衛生コンサルタント会から受験準備用図書として過去問題集などが販売されているので、購入して勉強をしましょう。
4.労働安全衛生診断に関するよくある質問
Q.労働安全衛生診断は受けないと罰則がありますか?
A.罰則はありませんが、受けておいた方が労働安全衛生対策に真面目に取り組んでいるとみなされるでしょう。
Q.労働安全コンサルタント・衛生コンサルタントを両方取得することは可能ですか?
A.可能ですがとても大変でしょう。医師の資格などを持っていれば別ですが、どちらか片方だけでも十分役に立ちます。
Q.労働安全コンサルタントに指導を頼むと料金はどのくらいですか?
A.ケースによりますので、事前にしっかりと業者と話し合ってください。
Q.労働安全コンサルタント・衛生コンサルタントを取得して独立することはできますか?
A.はい、可能です。
Q.コンサルタントの資格を取得したいのですが予備校はありますか?
A.残念ですが労働安全・衛生コンサルタントの資格は受験者自体が少なく、授業を行っている予備校はありません。その代わり受験セミナーや受験対策を行っている団体は多数存在します。
5.おわりに
いかがでしたか。今回は労働安全衛生診断についていろいろとご紹介しました。より安全に・快適に・衛生的に仕事を行うためには、労働安全衛生診断はおすすめです。労働災害防止にはもちろんのこと、安全管理・衛生管理がうまくいっていない事業所は診断を受けたり指導を申し込んだりするとよいでしょう。
無料登録でキャリアアップへの一歩を!

現在よりも好条件な職場に転職したい方や、未経験から新しい職種に挑戦したい方におすすめなのが転職エージェントサービスです。
中でも『マイナビエージェント』は求人数が業界トップクラスで、転職活動全般をサポートするサービスも充実!
非公開求人を豊富に保有しており、一般公開されない優良求人を逃すことなくチェックできます。
すぐに転職予定がない方も相談に乗ってもらえるため、早めに登録しておくことで、よりマッチ度の高い求人を紹介してもらいやすくなります。
関連記事
- 2017/02/25 【徹底解説】労働安全コンサルタントの年収や給料は?取得方法と共に解説します!
- 2017/03/28 安全衛生管理計画とは? 作成方法や提出の仕方を詳しく解説
- 2015/11/30 エレベーターの法定点検の内容は?項目・やり方をチェック!
- 2016/06/24 防災・消防設備の点検の方法が知りたい!点検期間や必要な資格とは?
- 2019/05/31 管工事施工管理技士の講習にはどんな種類がある? 参加方法を解説!