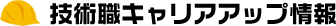貫流ボイラーの仕組みや特徴は? 取り扱える資格とともに紹介
2016/01/01
暖房や給湯など、我々の日常生活における温まりの源、それがボイラーです。中でも、貫流ボイラーはその効率と柔軟性からさまざまな場所で活躍しています。でも、具体的に何がどうなっているのか、しっかりと理解できていますか?
そこで、今回は貫流ボイラーの仕組みや特性に焦点を当て、その魅力をご紹介します。さらに、ボイラーの適切な制御方法についても掘り下げていきます。
ボイラー技士を目指す皆様や、ただ単純にこの仕組みに興味がある皆様にとって、この記事が深い理解を促し、実生活に役立つ情報の提供に繋がればと思います。
1.貫流ボイラーとそのほかのボイラーの違いは?
前述したように、ボイラーとは燃料で水を熱して蒸気や温水を発生させる装置です。ちなみに、給湯器もボイラーの一種ですが水蒸気が発生しないので「無圧ボイラー」といって区別されています。ボイラーは水を沸かして蒸気を発生させますが、水がすべて蒸気になるわけではありません。そこで、水蒸気になれなかった水をドラム内で循環させて再び熱する方式のボイラーもあります。これを、循環式ボイラーというのです。
一方、貫流式ボイラーは水を循環させるドラムがありません。水は一方的に給水装置から管の中を通り、熱せられて蒸気になります。蒸気になれなかった水はそのまま排出されてしまうのです。「貫流」とは水が貫くという意味。つまり、貫流ボイラーは、水の循環がないボイラーのことをいいます。
2.貫流ボイラーのメリット・デメリットは?
では、貫流ボイラーはどのような特徴があるのでしょうか? この項では、メリットとデメリットとに分けてご紹介します。
2-1.貫流ボイラーのメリットは?
循環式ボイラーの場合は構造上、常に水を循環させる必要があります。ですから、すべての水が蒸気になってしまわないように大量の保水が必要です。一方、貫流ボイラーは保有水量が少なくて済みます。ですから、より早く蒸気を発生させることができるでしょう。
また、ドラムがない分ボイラー自体もコンパクトになっています。ですから、スペースが狭い場所でも問題なく置けるでしょう。水と蒸気の比重の差がない超臨界ボイラーなどにも使われています。
2-2.貫流ボイラーのデメリットは?
貫流ボイラーは、水を循環させることなく蒸気を発生させます。ですから、水の量が少しでも変われば、水蒸気の量や温度が変わってしまうでしょう。職場によっては水蒸気の量や温度を長期安定させないと不具合が生じることもあります。ですから、気候や外気温、さらに給水の温度によってボイラーに流す水の量や燃料の温度などを調節しなければなりません。このバランスを安定させるには、高い制御技術が必要です。そのため、貫流ボイラーを取り扱うには、資格だけでなく長年の経験が必要になります。
また、同じボイラーでも、年式や構造などが違えばバランスも微妙に変わってくるでしょう。ですから、機材を新しくしたり、長年制御してきた人が辞職してしまったりすると、ボイラーに不具合が生じやすくなることがあります。
3.超臨界ボイラーってどこで使われるの?
超臨界ボイラーとは、水の臨海圧以上の高圧蒸気を発生させる装置です。一般的にボイラーを使って蒸気を発生させるためには、水を沸騰させます。しかし、超臨界ボイラーの場合は、超高熱によって沸騰する間もなく水を蒸気にしてしまうのです。水蒸気の温度は100度以上になるため、多少熱が下がっても水に戻りません。つまり、効率よくエネルギーを得ることができるのです。
超高熱で水を直接蒸気にしてしまうので、循環方式は使えません。すべて貫流ボイラーになります。超臨界ボイラーが使われる代表的な場所、といえば火力発電所です。火力発電所は、蒸気の力でタービンを回して電気を作ります。このタービンを回す蒸気を作っているのが、超臨界ボイラーです。大量の電気を安定して供給し続けるには、循環式ボイラーでは不十分となります。
また、超臨界ボイラーも非常に高度な制御技術が必要になります。今は、コンピューターで制御されたタービンも多いですが、最後に頼りになるのは人の経験でしょう。つまり、経験のあるボイラー技術者は、いろいろなところで需要があるのです。
4.貫流ボイラーを扱うための資格は?
貫流ボイラーを扱うには、ボイラー技士の資格を取得しなければなりません。貫流ボイラーは、伝熱面積の大きさによって2つに分けられています。ちなみに、伝熱面積とは熱交換装置の伝熱に寄与している表面の面積のこと。これが大きいほど伝熱量が大きいことになります。
ボイラー技士は、特級、一級、二級の3種類があり、250平方メートル以上の伝熱面積を持つ貫流ボイラーは、特級と一級のボイラー技士しか扱えません。250平方メートル未満ならば、ボイラー技士であれば扱えるのです。大きなボイラーを扱っている職場に就職したり転職したりする場合は、特級や一級のボイラー技士の資格を取得しておくとよいでしょう。
5.ボイラー技士の資格を取得するには?
ボイラー技士は、ボイラーの取り扱いや点検、安全管理を行える資格です。原則として、伝熱面積25㎡以上のボイラーを設置している事業場では、必ずボイラー技士の資格を持つ作業主任者の選任が必要となります。伝熱面積25㎡未満であっても、小規模ボイラーの規格を超える設備に該当すれば選任が必要です。また、特例として、貫流ボイラーの伝熱面積の基準は通常の10分の1に換算が可能。
なお、ボイラーにかかわる資格には、このほかにボイラー溶接士やボイラー整備士があります。しかし、ボイラーを取り扱うことができるのは、ボイラー技士だけですので混同しないように注意しましょう。ボイラー技士になるためには、試験を受けて免許を交付してもらわなければなりません。ボイラー技士の試験は、二級ならば特に受験資格はいらないのです。
ただし、18歳未満は合格しても講習を受けたりすることはできません。一級と特級は試験を受けるのにも実務経験や学歴が必要なので注意してください。
また、ボイラー技士の試験に合格しても、未経験者の場合は一定の講習を受ける必要があります。この講習は職業訓練校でも実施されていますので、講習を受けてから試験にチャレンジする人も多いでしょう。職業訓練校で開設されている資格講座の中でも、特に人気がある講習です。さらに、二級ボイラー技士の資格を取得して実務経験を積めば、一級や特級の受験資格が与えられます。ですから、全く異なる分野の職種からボイラー技士に転職しようとする場合は、まず二級の免許を取得してステップアップしていくとよいでしょう。
貫流ボイラーの仕組みや特徴まとめ
今回は貫流ボイラーの構造や仕組みについてご説明しました。ボイラーは事業所などに見られる設備の中でも、あまり目立つ場所に置かれることはありません。しかし、ボイラーがなければ給湯や暖房などの設備を動かすことができないことも多いのです。
また、ボイラーは蒸気を発生させる装置ですから、安全対策を怠れば爆発事故の危険性があります。今は、技術の進歩によってより安全性の高いボイラーが作られるようになりました。しかし、機材は劣化するものですから、日頃のメンテナンスが大切です。
ボイラー技士の方は貫流ボイラーを取り扱う機会があれば、ぜひチャレンジしてみましょう。貫流ボイラーを自由に取り扱えるようになれば、その腕を見込まれて出世や転職のチャンスも広がります。
無料登録でキャリアアップへの一歩を!

現在よりも好条件な職場に転職したい方や、未経験から新しい職種に挑戦したい方におすすめなのが転職エージェントサービスです。
中でも『マイナビエージェント』は求人数が業界トップクラスで、転職活動全般をサポートするサービスも充実!
非公開求人を豊富に保有しており、一般公開されない優良求人を逃すことなくチェックできます。
すぐに転職予定がない方も相談に乗ってもらえるため、早めに登録しておくことで、よりマッチ度の高い求人を紹介してもらいやすくなります。
関連記事
- 2016/09/29 ボイラー技士の免許を取ろう!資格取得に必要な知識とコツを解説!
- 2016/02/22 丸ボイラーってどんなボイラーなの?構造や仕組みをわかりやすく解説!
- 2024/12/17 ボイラータービン主任技術者の難易度は?合格への具体的なコツとは
- 2017/04/17 ボイラーの点検・メンテナンス方法を知ろう! 必要な資格は?
- 2015/11/26 ボイラーの検査にはどのような種類があるの?事業者が行える?